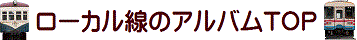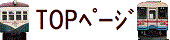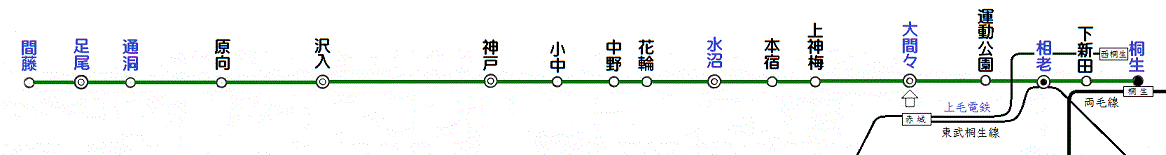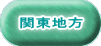わたらせ渓谷鐵道
両毛線の桐生から栃木県日光市の間藤まで44.1kmを結んでいます。
1912年に足尾鉱山の鉱石輸送を目的に足尾鉄道として開業。
1913年に国が借り入れ、足尾線になりました。
1918年に国が買収。
1973年足尾銅山閉山。
1987年国鉄分割民営化によりJR東日本が継承。
1989年にJR東日本足尾線を第三セクターに転換し、わたらせ渓谷鐵道開業。
足尾銅山盛業中は銅の精錬に伴う亜硫酸ガスのため、はげ山が広がり、日本の公害問題の原点でしたが、今はかなり緑が回復して来ています。足尾銅山は途中の通洞にあり、「足尾銅山観光」としてかっての銅山の坑内を見ることが出来ます。
清流を取り戻した、渡良瀬川に沿って走る絶景路線です。
写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。
トロッコわたらせ渓谷号
DE101537+わ99形5010+5020+5070+5080
DE101537は、1998年に「トロッコわたらせ渓谷号」牽引用としてJRより購入。客車は5010と5080が元スハフ12、5020と5010はなんと元京王の5000系です。
2015年9月21日撮影 通洞~原向


わ89-310形312
1990年富士重工製のLE-DC。
開業時に導入されたLE-CarⅡわ89-100形、200形を置き換えました。各車に愛称がつけられており、312の愛称は「あかがねⅡ」。5両製造され、主力で運用されていますが、老朽化も進んでおり312は2019年廃車。
2016年1月3日撮影 桐生


わ89-310形312
1990年富士重工製のLE-DC。
開業時に導入されたLE-CarⅡわ89-100形、200形を置き換えました。各車に愛称がつけられており、312の愛称は「あかがねⅡ」。5両製造され、主力で運用されていますが、老朽化も進んでおり312は2019年廃車。
2016年1月3日撮影 桐生
わ89-310形311+わ89-310形314
わ89-310形314は1993年富士重工製。「あかがねⅢ」。相老で東武桐生線と連絡しています。
2015年9月21日撮影 相老


WKT510形511+WKT-550形551
トロッコわっしー1号。 トロッコと言っても窓がオープンなだけで立派な気動車。 WKT550は人気のトロッコ列車の増発用に2012年導入。 WKT510形は2013年導入。もっぱら「トロッコわっしー」のWKT550のお相手役を務めています。
2015年5月3日撮影 相老


2015年9月21日撮影 相老


WKT-550形551+WKT-510形511 わ89-310形311
トロッコわっしー1号は新緑を求める観光客で満員でした。
2015年5月3日撮影 相老


WKT-550形551+WKT-510形511 わ89-310形311
トロッコわっしー1号は新緑を求める観光客で満員でした。
2015年5月3日撮影 相老
WKT500形501
2011年新潟トランシス製NDC。WKT510形が導入されるまで、トロッコわっしーWKT550形のお相手役でした。
2015年9月21日撮影 相老


WKT500形501
2011年新潟トランシス製NDC。WKT510形が導入されるまで、トロッコわっしーWKT550形のお相手役でした。
2015年9月21日撮影 相老
わ89-310形312
2015年9月21日撮影 大間々


わ89-310形315
1993年富士重工製のラストナンバー「わたらせⅢ」。
2015年9月21日撮影 大間々


わ89-100形101
1988年富士重工製のLE-CarⅡ。
2013年に運用を離脱し、大間々で保存されています。
ボギ-車のLE-CarⅡはいすみ鉄道いすみ200形等、全国の第三セクターで採用されましたが、廃車が進み、残りはわずかになっています。わたらせ渓谷鐵道でも101を最後に全車廃車されています。
2015年9月21日撮影 大間々


わ89-100形101
1988年富士重工製のLE-CarⅡ。
2013年に運用を離脱し、大間々で保存されています。
ボギ-車のLE-CarⅡはいすみ鉄道いすみ200形等、全国の第三セクターで採用されましたが、廃車が進み、残りはわずかになっています。わたらせ渓谷鐵道でも101を最後に全車廃車されています。
2015年9月21日撮影 大間々
わ89-300形302
開業時に用意されたイベント対応車。
富士重工製のLE-DC。
2015年廃車。大間々で保存されています。
2015年9月21日撮影 大間々


トロッコわっしー1号
WKT550形551+WKT510形511
2015年5月3日撮影 通洞


WKT500形501
2015年9月21日撮影 通洞