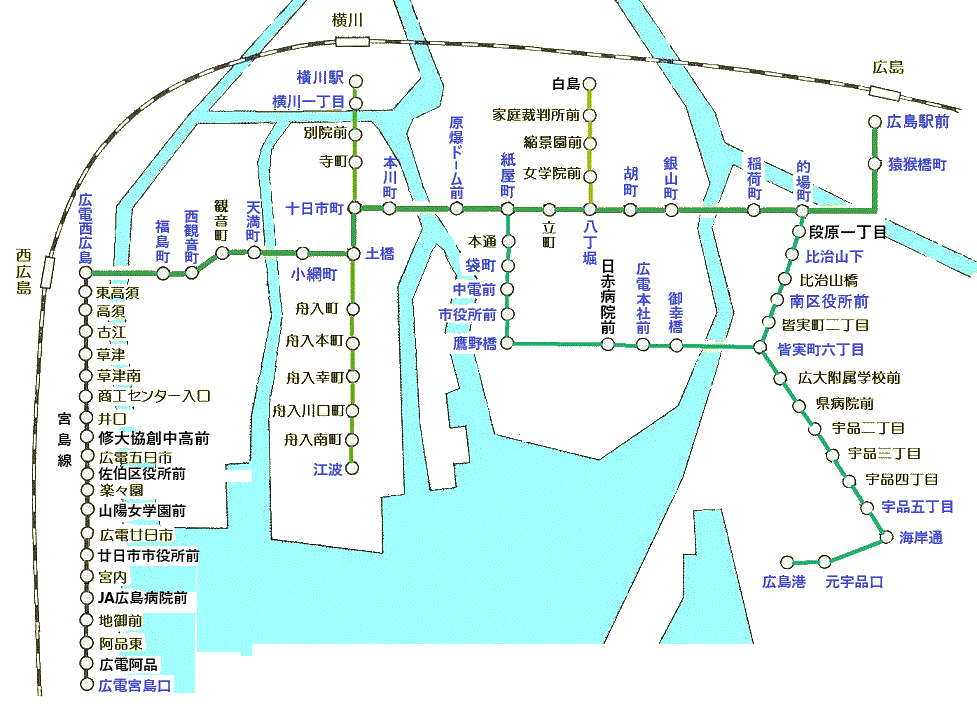広島電鉄
日本最大の規模を持つ広島の路面電車です。
全国で不要になった路面電車を集め、塗装も前のまま運行しており、動く電車の博物館と言われています。京都市電1900形、大阪市電2601形、神戸市電1150形等、広島に行けば往事とあまり変らない姿を見る事ができます。
また、鉄道線である宮島線と直通運転を行い、今ではほとんどが直通車となり、鉄道線の電車を全部路面型の電車に置き換えてしまいました。かっての鉄道線の車両は「ローカル線のアルバム」に掲載しています。
黒字経営を続け、最近では超低床車の新車の投入も活発に行っており、今、各地で起こっている路面電車見直しの動きの先駆けになっています。また、他社では超低床車の導入にあたり、新潟トランシスのLRVかアルナ車両のリトルダンサーシリーズの採用事例が圧倒的に多いのですが、広島では近畿車輛・三菱重工業・東洋電機製造・広島電鉄が共同開発したJTRAMを採用しているのも特徴です。
青字にリンクしています。
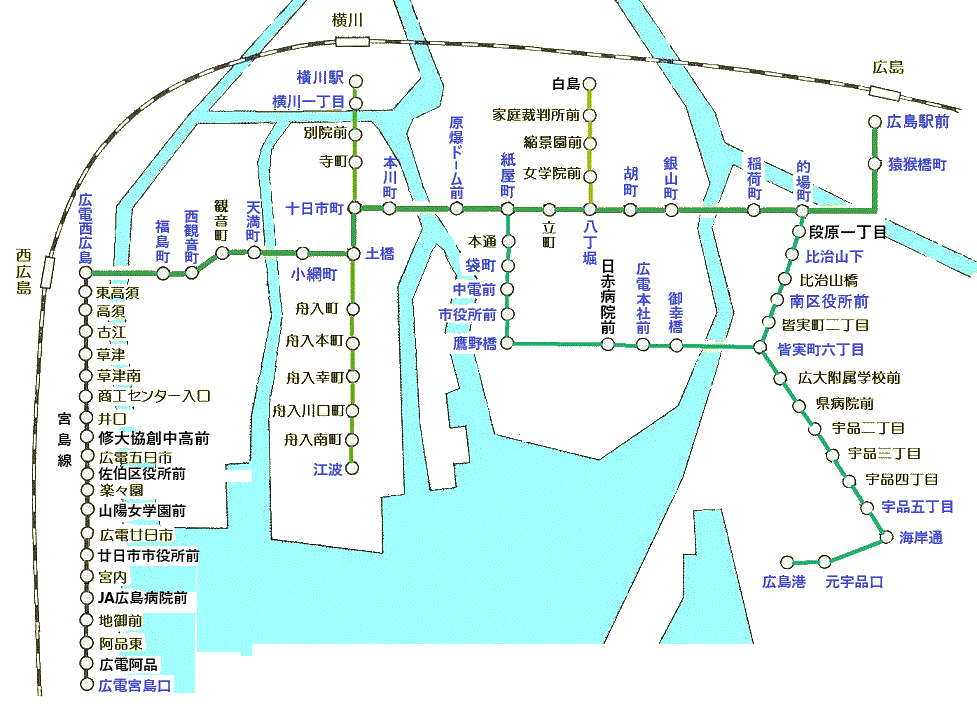
写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。
1000形1012 350形352
2024年12月16日撮影 十日市町


350形
1958年ナニワ工機(現アルナ車両)製。 宮島線直通用の850形として3両製造。 2000形、2500形の登場により、市内線用となり、 1971年に型式も350形となりました。 直通時代の名残として、菱形パンタグラフを装備していましたが、シングルアームに換装されています。2025年現在352のみ冷房化され現役です。
350形352
2024年12月16日撮影 横川1丁目


2024年12月16日撮影 十日市町


570形
元神戸市電500形。神戸市電500形は1920年から製造され、製造年次毎に6グループに分かれます。その内、1924年以降に製造され、1958年~62年に車体更新された3グループ17両が1971年~73年にかけて移籍。1985年から廃車が始まり、2025年現在、582のみ在籍しており、朝夕のラッシュ時中心に運用されています。
570形582
元は1924年製の神戸市電500形592。1971年譲受。1950年台に改修を受け、鋼板は張り替えられていますが、躯体は製造から100年経っています。冷房化もされており、朝夕の運用に入っています。
2024年12月15日撮影 広電本社前


2025年2月28日撮影 寺町


650形
1942年木南車両製。5両製造されました。1945年8月6日の原爆投下で全車被爆し、全半壊しましたが、1948年までに全車復旧されています。この内655は1967年に事故廃車。2006年に654が廃車されましたが、広島市交通科学館で保存。2025年現在、651,652,653の3両が在籍しています。
650形651
2025年現在、朝夕のラッシュ時に、主に広電西広島~日赤病院前で運用についています。
2025年10月6日撮影 千田車庫


2025年10月7日撮影 十日市町~本川町


650形652
2025年現在、朝夕のラッシュ時に、主に広電西広島~日赤病院前で運用についています。千田車庫の写真では後ろに750型768 TRAIN ROUGEが見えています。
2025年10月6日撮影 千田車庫


2025年10月7日撮影 十日市町


650形653
2025年現在、一般運用からは外れ、被爆時の塗装に復刻されイベント用として主に貸し切りで運用されています。
2024年12月15日撮影 鷹野橋


2024年12月15日撮影 鷹野橋


江波車庫
左の51は元大阪市電1600形1643の750形759を1980年頃に貨50形に改造。花電車に使用されています。
2024年12月16日撮影


庫内に1925年梅鉢鉄工所製の150型156が見えています。被爆電車で1971年に廃車されましたが1987年に復籍し、イベントで走行することがあります。
2025年10月6日撮影


750形
元大阪市電1601形10両、1651形4両、1800形8両計22両を1965年~67年に譲受。主力として活躍していました。。758、759の2両が貨50形に改造。768がイベント用「TRAIN ROUGE」に改造され現役。762が2025年現在、現役として市内線で運用されています。それ以外は一部は700形(2)に機器を譲り、2015年までに廃車。772は廃車後ミャンマーへ譲渡されています。また、元大阪市電1601形には南海電鉄→阪堺電気軌道モ121形があります。
750形762
1940年木南車輛製の元大阪市電1651形1652。
2024年12月16日撮影 横川一丁目


2024年12月16日撮影 横川一丁目~横川駅


900形
元大阪市電2601形を1969年に14両譲受。913が2025年現在現役で運用されています。それ以外は2020年までに廃車。元大阪市電2601型には鹿児島市電800形があります。
900形913
2024年12月15日撮影 鷹野橋


2024年12月16日撮影 十日市町


1150形
元神戸市電1150形を1971年に7両譲受。550形、1100形と一緒に神戸市電廃止直後に移籍しました。2025年現在二代目ハノーバー電車となっている1156のみ在籍しており、ラッシュ時に運用されています。それ以外は2003年までに廃車。
1150形1156
2024年12月15日撮影 牛田車庫


2025年2月28日撮影 土橋


1900形
元京都市電1900形を1978年の京都市電廃止後15両譲受。広島に来てから冷房化されています。京都市電1900形は900形916~931をワンマン改造し番号を引き継いだため、1916から始まっていましたが、広電にきて1901~に整理されています。全車揃って活躍していましたが、2024年から廃車が始まっています。
1900形1901
元京都市電1916。
2024年12月16日撮影 紙屋町


2024年12月16日撮影 宇品五丁目


2024年12月16日撮影 元宇品口


1900形1905
元京都市電1919。
2024年12月16日撮影 皆実町六丁目


2024年12月17日撮影 紙屋町


1900形1906
元京都市電1920。
2024年12月17日撮影 十日市町


2025年2月28日 土橋


1900形1907
元京都市電1924。
2024年12月16日撮影 皆実町六丁目


2024年12月17日撮影 紙屋町


1900形1908
元京都市電1921。
2021年3月31日撮影 天満町


2024年12月15日撮影 中電前


1900形1913
元京都市電1929。
2025年2月27日撮影 土橋~十日市町


1900形1914
元京都市電1930。
2024年12月15日撮影 八丁堀


2024年12月16日撮影 江波


700形
1982年から1983年までアルナ工機(現アルナ車両)で7両製造されました。元大阪市電の750形のモーターを流用し、駆動も吊掛け式です。その後1985に711~714の4両製造されましたが、こちらはモーターも新品でカルダン駆動と実質別形式です。新製時は菱形パンタグラフを装備していましたが、シングルアームに換装されています。
700形701
2024年12月17日撮影 横川


2024年12月15日撮影 稲荷町


700形702
2024年12月16日撮影 皆実町六丁目


700形703
2024年12月16日撮影 南区役所前


700形704
2024年12月15日撮影 広電本社前


700形705
2024年12月15日撮影 御幸橋


700形706
2025年2月28日撮影 八丁堀


700形707
2024年12月16撮影 横川駅


700形711
2025年2月28日撮影 八丁堀


700形712
2024年12月16撮影 十日市町


700形713 1900形1904
2024年12月15日撮影 横川駅


700形714
2025年2月28日撮影 江波車庫


800形
700形に続き、1983年~1997年迄アルナ工機(現アルナ車両)で14両製造されました。700形と基本同じ車体ですが、最初からZパンタを装備、また、ヘッドライトの位置等、細かい違いがあります。この後、増備は基本連接車になっており、2025年時点で最後の新製単車となっています。
800形802
2025年10月7日撮影 比治山下


2025年10月6日撮影 広電本社前


800形803
2025年2月28日撮影 銀山町


800形805
2024年12月17日撮影 原爆ドーム前


800形806
2024年12月15日撮影 八丁堀


800形807
2024年12月15日撮影 袋町


800形808
2024年12月16日撮影 紙屋町


800形809
2024年12月15日撮影 稲荷町


800形810
2024年12月16日撮影 皆実町六丁目


800形811
2024年12月15日撮影 広電本社前


800形812
2024年12月16日撮影 皆実町六丁目


800形813
2025年廃止区間。
2024年12月15日撮影 猿猴橋町


800形814
800形ラストNo。
2025年10月7日撮影 十日市町


200形
1988年に姉妹都市のドイツ ハノーバー市より寄贈された4輪単車です。1950年西ドイツDUEWAG社製。イベント用に使用されています。
200形238
2024年12月15日撮影 牛田車庫


3000形
西鉄福岡市内線の連接車、1101形・1201形・1301形を1976年に譲受け、1979年~82年にかけて3車体連接に改造された車両です。1980年代には宮島線直通の主力車両として活躍しました。3700型以降の連接車の登場により、1998年には市内線専用となり、2025年現在、3003ACB1編成が在籍するのみとなっていますが、ICカードに対応しておらず、運用を離脱しています。
3000形3003BCA
元西鉄1200形1203A,1206B,1206Aを1980年に3車体連接化。この日は荒田車庫で入れ替えに使用されていました。
2025年2月27日撮影 荒手車庫


2025年2月27日撮影 荒手車庫


3100形
1985年~86年に2500形2501~2510の2506を除く9両を3車体連接化しました。朝夕のラッシュ時中心に市内線で運用されています。
3100形3101BCA
1985年に2500形2505,2502,2501をB,C,Aに改造。竣工時の姿に復刻塗装されています。
2024年12月17日撮影 紙屋町


3100形3102BCA
1986年に2500形2504,2507,2503をB,C,Aに改造。
2024年12月17日撮影 原爆ドーム前


3100形3103BCA
1986年に2500形2510,2508,2509をB,C,Aに改造。
2024年12月17日撮影 本川町~原爆ドーム前


3700形
1984年~1987年にアルナ工機(現アルナ車両)で5編成製造されました。3500形に次ぐ連接車(ぐりーんらいなー)です。3500形は扱いが難しく、2012年に運用を離脱していますが、3700形は2025年時点でも宮島線直通の主力車両として活躍しています。
3700形3701BCA
1984年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2025年10月6日撮影 土橋


3700形3702BCA
1985年アルナ工機(現アルナ車両)製。広電宮島口駅は2022年に移転、新築され、面目を一新しています。
2024年12月16日撮影 広電宮島口


3700形3703ACB
1986年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 西観音町


3700形3704BCA
1987年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 小網町


3700形3705BCA
1987年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 福島町


3800形
1987年~1989年にアルナ工機(現アルナ車両)で9編成製造されました。広電初のVVVFインバーター制御車です。2025年現在、宮島線直通車として活躍中です。
3800形3801ACB
1987年アルナ工機(現アルナ車両)製。3801のみ行先表示器の位置が違っています。また、行先表示がLED化。
2024年12月16日撮影 紙屋町


3800形3802BCA
1987年アルナ工機(現アルナ車両)製。行先表示はLED化。
2024年12月16日撮影 宇品五丁目


3800形3803BCA
1987年アルナ工機(現アルナ車両)製。1987年製はヘッドライトが丸形。行先表示はLED化。
2025年2月27日撮影 銀山町


3800形3804ACB
1988年アルナ工機(現アルナ車両)製。1988年製からヘッドライトは角型のコンビネーションライトに変更。
2024年12月15日撮影 千田車庫


3800形3805BCA
1988年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 原爆ドーム前


3800形3805BCA
地上の広島駅前電停も2025年8月まで。
2021年3月31日撮影 広島駅前


3800形3806ACB
2025年8月に開通した広島駅2階へ直通するルート。
2025年10月6日 稲荷町


3800形3807BCA
1989年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 皆実町六丁目


3900形
1990年~1996年にアルナ工機(現アルナ車両)で8編成製造されました。3800形を出力アップしたマイナーチェンジ車です。3900形まで車体の表示が「ぐりーんらいなー」とひらがなです。2025年現在、宮島線直通車として活躍中です。
3900形3901BCA
1990年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月15日撮影 稲荷町


3900形3902ACB
1990年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 原爆ドーム前


3900形3903BCA
1991年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 天満町


3900形3904BCA
1992年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 西観音町


3900形3905BCA
1992年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2025年10月7日撮影 十日市町


3900形3906BCA
1995年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2025年10月6日撮影 稲荷町~広島駅


3900形3907ACB
1996年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 西観音町


3900形3908BCA
1996年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 天満町


3950形
1997年~1998年ににアルナ工機(現アルナ車両)で6編成製造されました。3900形のデザインを変更した車両で性能は同じですが、印象が大きく変わりました。車体の表示も「Green Liner」とアルファベット表示です。この後は超低床車が増備され、最後の連接車になっています。
3950形3951ACB
1997年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2025年2月28日撮影 胡町


3950形3953BCA
1998年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2025年2月27日撮影 十日市町


3950形3954ACB
1998年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2021年3月31日 胡町


3950形3955BCA
1998年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月16日撮影 広電西広島


3950形3956BCA
1998年アルナ工機(現アルナ車両)製。
2024年12月15日撮影 猿猴橋町


広島港
2003年に広島港宇品旅客ターミナル前に移転し200m位延長されました。全面屋根付の立派な電停です。
2024年12月16日撮影


超低床車
5000形
1999年~2002年にドイツのシーメンス社で12編成が製造された、広電初の超低床車「GREEN MOVER」。全国でも熊本市電9700形に次いで2例目です。5車体6軸(3台車)の構造で2車体は台車のないフローティング車体となっています。海外製のため、整備が難しく、2025年現在、3編成のみ主に宮島線直通で運用中。5007は部品取りになっていましたが、2025年に解体されています。
5000形5004BDECA
1999年導入。2025年現在ICカード非対応で運用離脱中です。
2016年11月6日撮影 原爆ドーム前


5000形5006BDECA
2001年導入。ICカードに対応しており、運用中。
2025年2月27日撮影 十日市町


5000形5008BDECA
2001年導入。ICカードに対応しており、運用中。
2024年12月17日撮影 原爆ドーム前


5000形5011ACEDB
2002年導入。ICカードに対応しており、運用中。
2024年12月16日撮影 西観音町


5100形
近畿車輛・三菱重工業・東洋電機製造・広島電鉄が共同開発した国産初のフルフラット超低床車JTRAM。全長30mで5000形と同じく5車体3台車の連接車です。愛称は「Green Mover Max」。2004年から2008年まで10編成が製造されました。主に1号線(広島駅前~紙屋町~広島港)で使用されていますが、一部は宮島線直通運用にもついています。
5100形5101BDECA
2004年導入。「Red Wing」(JR西日本227系)のラッピング。
2024年12月16日撮影 本川町


5100形5104BDECA
2005年導入。プロ野球広島カープのラッピング。
2024年12月16日撮影 広島港


5100形5105BDECA
2007年導入。
2024年12月15日撮影 御幸橋


5100形5106BDECA
2007年導入。
2021年3月31日撮影 御幸橋


5100形5107ACEDB
2007年導入。被爆井戸の残る猿猴橋付近。この区間は2025年8月の広島駅乗り入れで廃止になります。
2025年2月28日撮影 的場町~猿猴橋町


5100形5108BDECA
2007年導入。Jリーグ サンフレッチェ広島のラッピング。
2024年12月16日撮影 胡町


5100形5109ACEDB
2008年導入。広島大学創立75+75年のラッピング。
2024年12月15日撮影 稲荷町


5100形5109ACEDB
2025年はNHK被爆80年プロジェクトのラッピング。
2025年10月6日撮影 銀山町


5100形5110ACEDB
2008年導入。広島交響楽団のラッピング。
2024年12月16日撮影 八丁堀


1000形
2013年から近畿車両・三菱重工・東洋電機で製造された5100形に次ぐ超低床車JTRAMです。市内線用に3車体となり18.6mの全長です。愛称は「GREEN MOOVER REX」。2020年までに18編成増備され、市内線の主力になっています。他の連接、超低床車と違い、車体にABCの記号がありません。
1000形1001
2013年導入。当初の塗装は赤紫で、愛称も小さいをイメージし「PICCOLO」でした。その後、塗装を変更し愛称も「GREEN MOOVER REX」。他車と違って前後で全面の塗分けが違い、片方は広電バス風。
2016年11月6日撮影 原爆ドーム前
1000形1001
2013年導入。当初の塗装は赤紫で、愛称も小さいをイメージし「PICCOLO」でした。その後、塗装を変更し愛称も「GREEN MOVER REX」。他車と違って前後で全面の塗分けが違い、片方は広電バス風。
2016年11月6日撮影 原爆ドーム前
2024年12月15日撮影 袋町


2024年12月16日撮影 海岸通


1000形1002
2013年導入。Flower Trainのラッピング。
2024年12月16日撮影 横川一丁目


1000形1003
2014年導入。標準塗装。
2024年12月16日撮影 紙屋町


1000形1004
2014年導入。標準塗装。
2024年12月15日撮影 稲荷町


1000形1005
2014年導入。標準塗装。地上の広島駅前電停もあとわずかです。
2024年12月15日撮影 広島駅前


1000形1006
2015年導入。標準塗装。
2024年12月17日撮影 八丁堀


1000形1007
2015年導入。標準塗装。
2024年12月15日撮影 鷹野橋


1000形1009
2016年導入。FORDAYSのラッピング。
2024年12月16日撮影 土橋


1000形1010
2016年導入。標準塗装。
2024年12月15日撮影 市役所前


1000形1012
2017年導入。標準塗装。この風景も2025年8月迄。
2024年12月15日撮影 猿猴橋町


1000形1014
2018年導入。標準塗装。
2021年3月31日撮影 広島駅前


1000形1015
2018年導入。
2024年12月15日撮影 八丁堀


1000形1016
2019年導入。標準塗装。
2024年12月16日撮影 比治山下


1000形1018
2020年導入。走る美術館「HIROSHIMA ART TRAM」
2025年2月27日 原爆ドーム前


5200形
2019年から導入されているJTRAMの3形式目。5100形と同じく全長30mで5車体3台車の連接車です。愛称は「Green Mover APEX」。2024年までに11編成導入され、主に宮島線直通車として運用されています。。
5200形5201BDECA
2019年導入。広電西広島から宮島線に入ります。以前は市内線は「己斐」宮島線は「広電西広島」と同じ場所でも違っていましたが、今は統一されています。
2024年12月16日撮影 広電西広島


2024年12月16日撮影 広電西広島


5200形5203ACEDB
2020年導入。
2025年2月27日撮影 胡町


5200形5204ACEDB
2020年導入。
2025年2月28日撮影 土橋


5200形5205ACEDB
2021年導入。
2025年2月28日撮影 十日市町


5200形5206ACEDB
2021年導入。2025年8月に開通した広島駅への駅前大橋ルート。
2025年10月5日撮影 広島駅


5200形5207BDECA
2022年導入。MOBIRYDAYS(広電が導入しているQRコード決済システム)のラッピング。
2024年12月15日撮影 的場町


5200形5209BDECA
2024年導入。
2025年2月28日撮影 八丁堀


5200形5210ACEDB
2025年導入。2月6日に搬入されたバリバリの新車です。
2025年2月28日撮影 荒手車庫


5200形5211ACEDB
2025年導入。3月15日運用開始のバリバリの新車です。
2025年10月7日撮影 本川町


2025年3月22日up
2025年10月8日写真追加 路線図書き換え










































 路面電車のアルバムTOP
路面電車のアルバムTOP 
 広島電鉄
広島電鉄 200形
200形 350形
350形 570形
570形 650形
650形 750形
750形 900形
900形 1150形
1150形 1900形
1900形 700形
700形 800形
800形 3000形
3000形 3100形
3100形 3700形
3700形 3800形
3800形 3900形
3900形 3950形
3950形 1000形
1000形 5000形
5000形 5100形
5100形 5200形
5200形