高松琴平電鉄
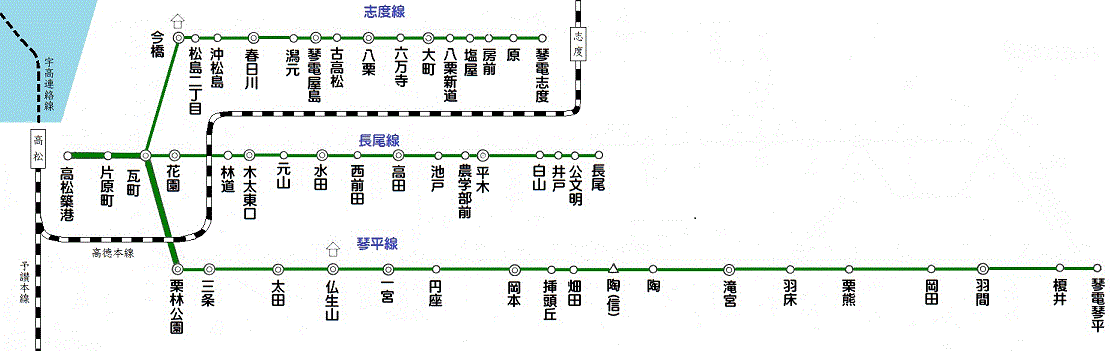
1943年に戦時統合により、琴平電鉄、高松電気軌道、讃岐電鉄の3社が統合され、設立。現在の琴平線、長尾線、志度線です。
四国ではもっとも路線延長の長い私鉄です。
車輌も前身からの引継ぎ車あり、自社発注あり、大手私鉄からの払い下げあり、廃止になった地方私鉄から来たものあり、とバラエティーに富んでいました。
1994年の瓦町駅改良工事の際、駅ビルに百貨店のそごうを誘致し、ことでんそごうを開店しましたが、2001年にそごうグループの破綻の影響を受け、琴電自身が民事再生法の適用を申請しています。
2006年には再生計画終了。盛業中です。
ここの形式と車番の関係は独特で、琴平線の場合、車番は形式より1桁少なく、かつ2桁目が進み、1桁目は0もしくは5。
長尾線、志度線は形式と車番の桁数は一致しています。その間で車輌の入れ替えがあり、複雑になっています。
まだ旧型車が活躍していた1984年の訪問です。
1984年5月2日 3日撮影
琴電琴平線
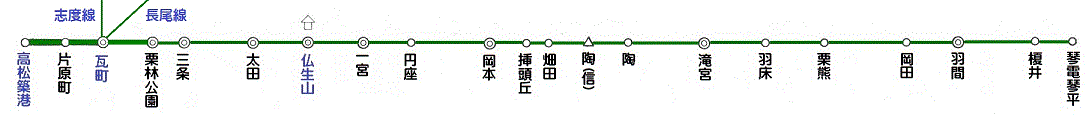
金刀比羅宮への参詣路線として、1926年に琴平電鉄として開業。高松築港から琴電琴平まで32.9kmを結んでいます。
途中瓦町で志度線、長尾線と連絡しています。この頃は志度線と直通運転していましたが、1994年の瓦町駅改良工事に伴い、志度線を分断し、長尾線と直通するようになりました。
高松築港から栗林公園まで複線です。
写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。
3000形
1984年5月撮影 片原町~高松築港
.jpg)
.jpg)
1020形×2+1060形
1020形は元名鉄3700形。1060形は元阪神5101形。高松築港~片原町は高松城の堀に沿って走っています。
1984年5月撮影 片原町~高松築港
.jpg)
.jpg)
820形
元豊川鉄道クハ100形→国鉄クハ5610形。
1984年5月撮影 片原町~高松築港
.jpg)
.jpg)
1050形
元阪神5001形。
1984年5月撮影 片原町~高松築港
.jpg)
.jpg)
1060形1061
1960年川崎車輌製の元阪神5101形5107。1981年入線。2006年廃車。
1984年5月撮影 瓦町


8000形810
1940年木南車輌製の元豊川鉄道クハ101→国鉄クハ5610。 国鉄時代は福塩線で使用されていました。1962年に譲受。1981年の更新で2灯化され、外観の印象が変わりました。2003年廃車。
1984年5月撮影 瓦町


8000形810
1984年5月撮影 仏生山


1020形1028
1957年から旧型の機器を流用し日本車輌で製造された元名鉄3700系ク2705。1020形は1969年~1973年に8編成16両が入線しています。2004年までに廃車。
1984年5月撮影 瓦町


1020形1027
元名鉄3700系モ3705。
1984年5月撮影 瓦町


950形960
元国鉄オハ31299。客車改造の制御車です。台枠のみ利用し車体は新製されています。1964年に譲受、1966年竣工。1984年廃車。
1984年5月撮影 仏生山


10000形1002
1952年日立製の自社発注車。琴平線の急行用として新製されました。こんぴら号」の愛称がありました。1986年廃車。
1984年5月撮影 仏生山


10010形1012+1011
1960年帝国車輌(現総合車輌製作所)製の自社発注車。今のところ琴電最後の自社発注車です。1011が電動制御車です。琴平線の急行用で、「こんぴら2号」の愛称がありました。 製造時は前面2枚窓の湘南顔でしたが、1979年に改造されています。2003年廃車。
1984年5月撮影 仏生山


1984年5月撮影 仏生山


5000形520
1928年加藤車輌製の自社発注車。1985年廃車。
1984年5月撮影 仏生山


デカ1
1957年自社製の電動貨車。仏生山車庫の入れ替え用として健在です。
1984年5月撮影 仏生山


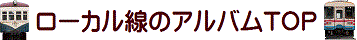
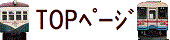
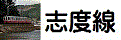
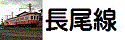

.jpg)






