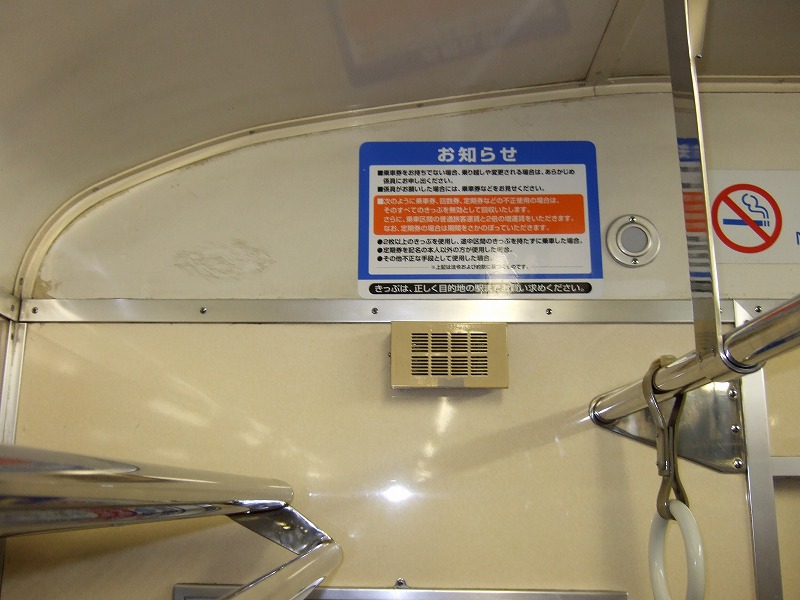471系3本、457系4本を含め3両組成で26編成ありましたが最初に編成ごとの見所さらには車両ごとの写真を並べて間違い探しのごとく紹介していきます。さしあたっての着目点として思いつくまま列挙しつつ代表的と思われる参考写真を並べてみました。(ここに記載の写真や車番は一例ですので他にも同様なタイプの車両が存在しています。詳細は個別車両の紹介写真を参照してください)
写真をクリックすると拡大画像が表示されます。写真の外側右下に表示される×マークをクリックすると戻ります。
大型前照灯を残した車両が多かった(多数存在)

クハ455-47
近郊型改造で車両両端のクロス座席がロング座席化されていましたが、クモハとクハは運転席側、モハはパンタグラフ側のロング座席の長手寸法が不足していたのか、妻壁との間に隙間ができてしまったようです。その隙間を埋める方法として多くは次のような処理で対応されていました。
・座面は板状の部材で継ぎ足したが、この部分に背当てのなかったタイプ

モハ474-17
・箱状機器箱のような造作物を作ったタイプ

クモハ457-18
・隙間をそのまま残したタイプ
・隙間をそのまま残したタイプ

モハ474-43

クモハ457-16
このうち隙間を残したままのタイプは少数派でした。(A14編成のクモハ、モハだけは特殊なので後述)
このうち隙間を残したままのタイプは少数派でした。(A14編成のクモハ、モハだけは特殊なので後述)
上記の近郊型改造に加え、A01~A09の9編成は乗降時間短縮策としてデッキ部分の扉を撤去し通路幅も拡大されました。
施工済

モハ470-1
未施工

クモハ457-16
通路幅が拡大された9編成については、車体側面のユニットサッシも交換されましたが、行程簡素化のためか窓隅のRがなくなり角状のユニットサッシとなったため、未改造車とは外観の印象が若干異なります。
サッシ交換済

モハ470-2
未施工

モハ456-18
・ただ、サハの妻面窓やクハの運転席側乗降扉前の小窓についてはサッシの交換が行われなかったと見られ窓隅がR型のままでした。
・ただ、サハの妻面窓やクハの運転席側乗降扉前の小窓についてはサッシの交換が行われなかったと見られ窓隅がR型のままでした。

クハ455-13

サハ455-4
・また、A09編成についてはクモハとモハは通路幅拡大とサッシ交換が行われたのにクハ455-19だけは従来どおりの姿のままで使用されていました。
・また、A09編成についてはクモハとモハは通路幅拡大とサッシ交換が行われたのにクハ455-19だけは従来どおりの姿のままで使用されていました。

クハ455-19
クモハ471形3両(471-1 471-2 471-9)には運転席に設けられた小窓上部に小さな庇状の樋が着いています。

クモハ471-1

クモハ471-2

クモハ471-9
※471系は雨樋が運転席の上部までなく短いためと思われる。
※471系は雨樋が運転席の上部までなく短いためと思われる。
新製時の荷棚には車両の長手方向に並ぶパイプ状の部材が使用されましたが、近郊型改造でロングシート化された車両の両端部はパイプ棚→金属製の網棚に交換されました。
ただ、A01~A04編成のサハ455についてはロングシート化された部分もパイプ棚(ステンレス製)でした。

サハ455-2
またクロス席についても
・クロス席部分も全部金属製の網棚に交換したタイプ

クモハ475-18
・クロス席はパイプ棚のままであるが部材をステンレス製に交換したタイプ

クモハ475-50
・クロス席はパイプ状で材質もそのままだったタイプ
などが見られます。

モハ456-16
デッキドアを廃し幅広通路化した車両は、クロス席とロング席の境目に位置するクロス席について、窓側の壁との隙間が塞がれています。
左端側に写っている席の背当て部に着目

クハ455-13
比較参考写真

クハ455-64
窓サッシは当初上段が下降、下段が上昇する構造でしたが、上段のみ固定化した車両、下段のみ固定化した車両も存在しました。
上下とも可動

クハ455-43
下段固定

クハ455-30
上段固定

クモハ475-45
運転席の換気不足問題があったのか、客席と運転席をつなぐダクトが客用デッキ扉上部に新設されました。該当車には運転席側の客室妻面上部にデッキ用と運転席用の二つの換気口が設けられています(仙台車も同様でした)

クハ455-61

クモハ471-1

クハ455-13
屋根上のベンチレータ(通風口)は最終的に全車とも撤去されたようですが、撤去時期にばらつきがみられました。
・編成によってクハは撤去されたがクモハやモハは残っていた。その状況は列車走行写真でも確認できます。
モハのみ無くクモハとクハに残る例

モハのみ残り両端のクモハとクハは無い例

クモハは無いがモハとクハは残る例

・モハ476では通風口が一気に撤去されず1個~2個だけ残したまま使われた時期がありました。
1個だけ残っていた例

モハ470-9
2個だけ残っていた例

モハ474-41
3個だけ残っていた例

モハ474-18
4個だけ残っていた例

モハ456-16
・モハ474-45には撤去した通風口の支持台だけ残されていた時期がありました。
・モハ474-45には撤去した通風口の支持台だけ残されていた時期がありました。

モハ474-45
・2個あるクモハ先頭部の角型通風口は1個だけ撤去して、撤去した側の通風器部分に支持台だけ残っていた時期がありました。
・2個あるクモハ先頭部の角型通風口は1個だけ撤去して、撤去した側の通風器部分に支持台だけ残っていた時期がありました。

クモハ475-53
天井に設置されたスピーカは当初の丸形から、八幡電気製の角型(両端はR付き)に交換された車があります。
両方が混在するケースもあります。

クハ451-33
モハ456-16はトイレ窓が塞がれていました。

モハ456-16
使用禁止になっていた洗面所については設備そのモノを撤去した車がある一方、使用禁止の注意書きを貼り洗面台を覆うことで利用できなくした車両がありました。
使用禁止の注意書き

クモハ475-43
使用禁止の注意書き

クモハ457-19
使用禁止の注意書き

モハ474-41
設備撤去

モハ456-18
トイレの使用を中止した車両については、客室内の妻面にトイレ使用表示灯は残されたものの、その表示は剥がされています。
使用不可
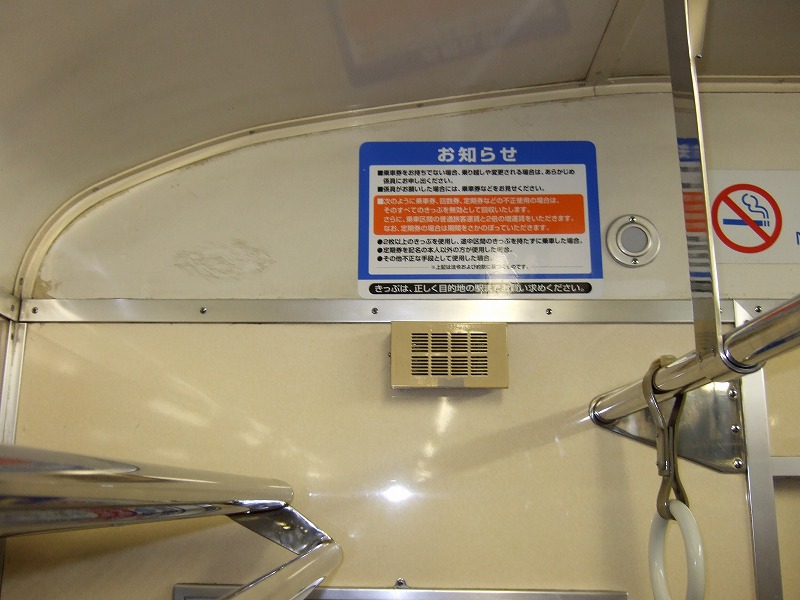
クモハ475-19
使用可能

クハ455-47
一部のモハには車体中央部に電光式行先表示器が取り付けられました。(クモハとクハには無し)なおJR西日本では側面の差し込み式行先表示板は使用していなかったようです。
基本的にトイレはクハを利用するような仕組みだったようなのでクモハやモハのトイレは使用不可でした。ただしトイレの仕切り壁や扉はそのまま存置され、床下に汚物処理タンクを搭載したままの車もあります。
汚物タンクが残されていた車で、トイレドアに業務用という表示のある車がありました。トイレ内はどうなっていたのか不明ですが、乗務員専用トイレだったのか?あるいは何らかの機器室になっていたのか?。

クモハ475-45

クモハ475-45

モハ474-41
洗面所側の窓ガラスは基本スリガラスのようですが透明ガラス化された車もありました。
車内にはデッキ扉脇に温度計が設置されていましたが、旧型の丸いアナログ計と新型の角型デジタル温度計が混在しています。
同一車両でも1位側と2位側で違うタイプを使用した例も見受けられます。
丸

クハ455-63
角

クハ455-63
A41編成のクモハとモハは両端ロングシートが旧型72系の部品流用ということ(通説)で吊り革支持棒が白塗り(ステンレスでなく鉄製?)で、その配置も他車と大きく異なっていました。ロング席端部の隙間も広くパイプで区切られています。ロングシート部分の荷棚については他の近郊型改造車が金属製の網だったのに対し、クロス席と同様のステンレスパイプが使われています。

クモハ475-41

クモハ475-41

クモハ475-41

モハ474-41
先頭車上部にある列車種別表示窓については、(氷柱により破損防止らしい)ガラスの代わりに鉄板で塞ぐ処置がなされました。塞ぎ後が判別できる車のほか氷柱切りと思われる庇付きの車も存在しました。最終的には全車?継ぎ目が判別できない平滑な仕上げになったようです。

クモハ475-46
継ぎ目無し

クモハ471-1
継ぎ目はっきり

クハ455-14
庇付き

クモハ475-51

 JR西日本の記録
JR西日本の記録