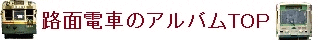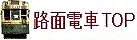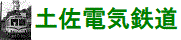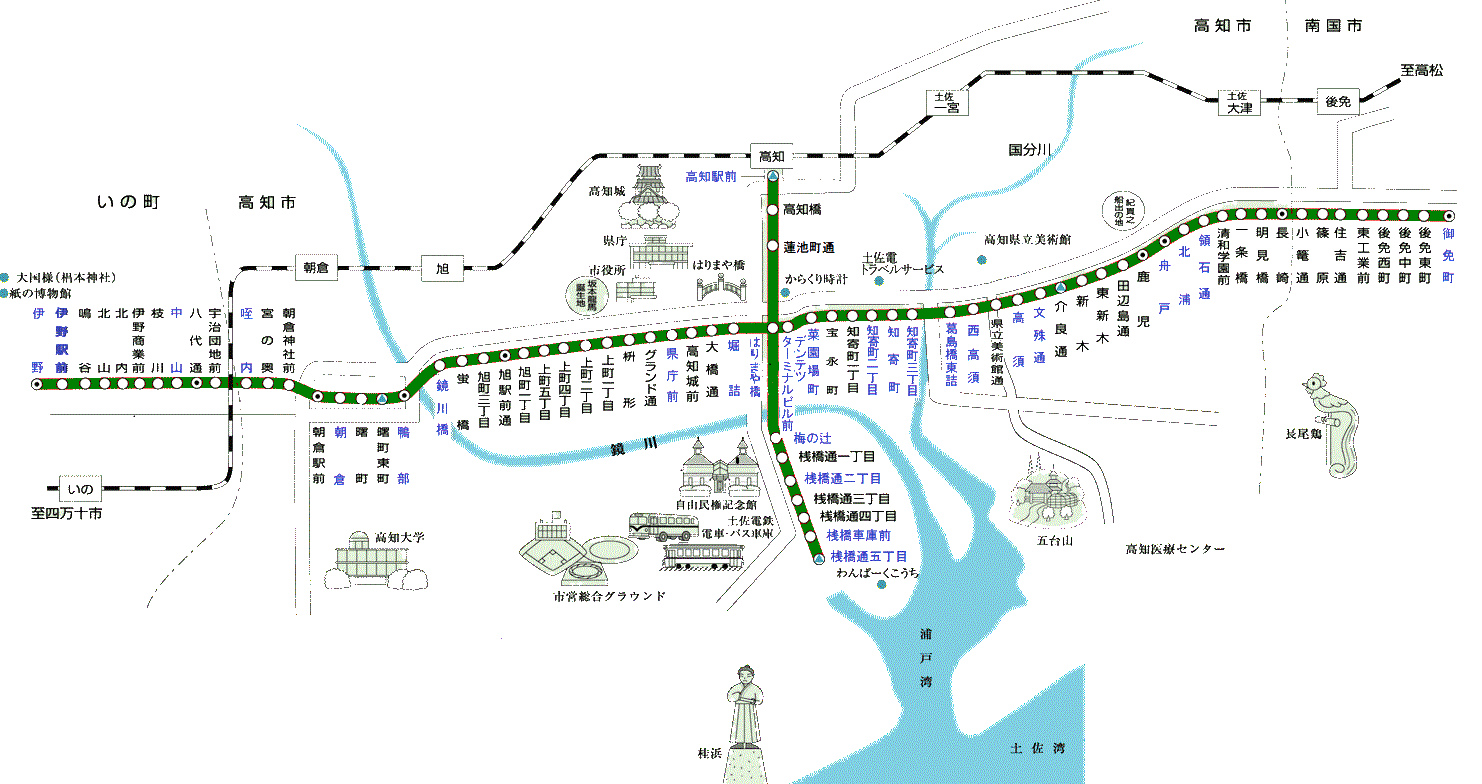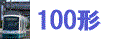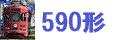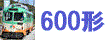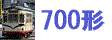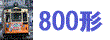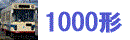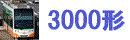とさでん交通
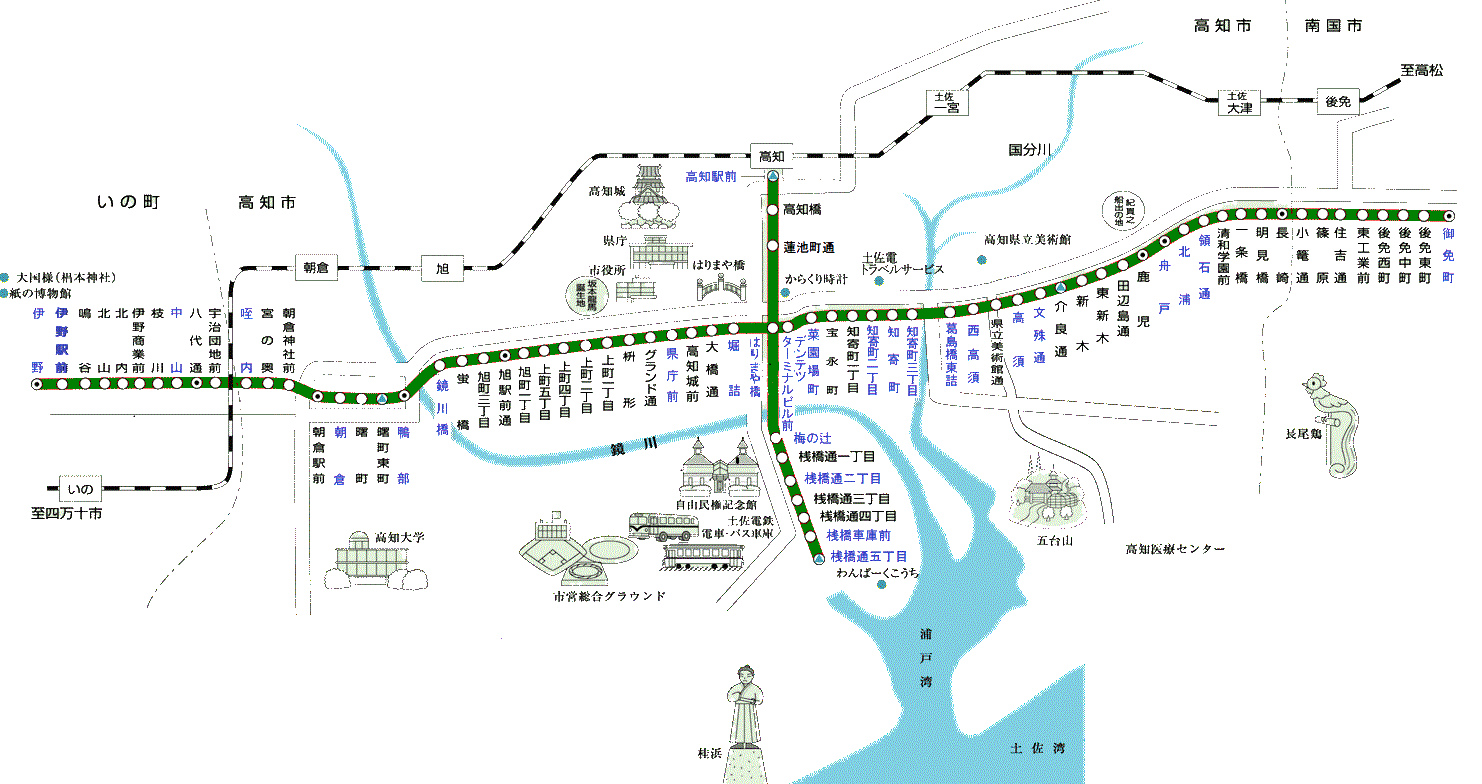
土佐の高知を走る路面電車です。
1904年の開業の土佐電気鉄道が2014年に第三セクター「とさでん交通」となりました。また、土佐電気鉄道時代の2001年に高知駅前電停が高知駅の正面ロータリーに移設され、便利になりました。
路線は土佐電気鉄道時代と変わらず桟橋線、伊野線、後免線の3線合計で22.4kmあります。
1978年以来40年ぶりの撮影ですが、電車は40年前のものがまだかなり残っています。車両の形式と青字の電停にリンクしています。
写真をクリックすると全画面表示されます。再度クリックで戻ります。ブラウザによっては拡大されない場合があります。
200形210 600形615 700形703
2022年10月14日撮影 はりまや橋


100形
2002年アルナ工機(現アルナ車両)製の超低床車 リトルダンサータイプL「ハートラム」。1編成のみ導入され、その後の超低床車は2021年に「ハートラムⅡ」として3000形が2編成導入されましたが、こちらはリトルダンサータイプUaとなりました。リトルダンサータイプLは長らく全国でこの1編成のみでしたが、2023年に福井鉄道がF2000形「Fukuramu Liner」として21年ぶりに導入しています。
100形101
2024年2月18日撮影 西高須


2024年2月18日撮影 菜園場町


200形
1950年~1954年にかけて21両導入された都電6000形のコピー車。215以降は自社工場製でしたが、すでに廃車されました。
冷房化されたものと非冷房のままのがあり、非冷房車は夏場は運行されない様です。
200形201
1950年日立製作所製。車体更新時に前面中央の窓が拡幅され、冷房化もされています。
2018年3月17日撮影 桟橋車庫前


200形202
1950年日立製作所製。201とほぼ同じです。
2018年3月17日撮影 高知駅前


200形206
1953年日立製作所製。ほぼ原形で非冷房。
2022年10月14日撮影 桟橋車庫


200形207
1953年日立製作所製。ほぼ原形で非冷房。2015年から復刻塗装の「金太郎塗り」になっています。
2024年2月18日撮影 桟橋車庫


200形208
1953年日立製作所製。ほぼ原形で非冷房。2018年は標準塗装でしたが、2022年は自社のラッピングになっていました。
2018年3月17日撮影 高須


2022年10月14日撮影 県庁前


200形208
高知城天守閣からの撮影です。
2022年10月14日撮影 県庁前


200形209
1953年日立製作所製。ほぼ原形で非冷房。
2022年10月14日撮影 桟橋車庫


200形210
1953年日立製作所製。なんと家庭用のクーラーで冷房化の試験車。屋根上に「室外機」が乗っています。
2022年10月14日撮影 梅の辻


200形211
1954年日立製作所製。211からパンタグラフが搭載されていますが、非冷房。
2018年3月17日撮影 はりまや橋


200形212
1954年日立製作所製。
2022年10月14日撮影 桟橋車庫


200形213
1954年日立製作所製。非冷房ですが、復刻塗装で活躍しています。1978年に撮影した200形で唯一の現役です。
2024年2月18日撮影 知寄町


200形214
1954年日立製作所製。
2018年3月17日撮影 高知駅前


590形
名鉄岐阜市内線、美濃町線で活躍していた590形を同線の廃止時(2005年)に譲受たもので、2両あります。主に桟橋線で運用。591は美濃町線時代にも撮影しています。
590形591
1957年日本車輌製の元名鉄モ590形591。2005年美濃町線廃止時に譲受。
2018年3月17日撮影 桟橋通二丁目


2024年2月18日撮影 桟橋車庫前


590形592
1957年日本車輌製の元名鉄モ590形592。
2024年2月18日撮影 桟橋車庫


600形
東京都電7000形(更新前)をモデルとして1957年から自社若松工場およびナニワ工機(現アルナ車両)で製造されました。
合計31両製造され、2023年現在29両が健在で、とさでん交通の主力車両です。全車両冷房化済みです。また、かって安芸線に乗り入れ用の連結運転可能な間接制御車と連結運転できない直接制御車があり、
現在、連結運転は行われていませんが、連結器の有無で区別できます。また、自社若松工場製車にはサイド窓の上段がHゴム支持のものとアルミサッシのものがある等、細かな形態の違いがあります。
600形601
1957年自社若松工場製。連結器があり、間接制御車です。
2024年2月18日撮影 知寄町3丁目


600形602
1957年自社若松工場製。連結器があり、間接制御車です。伊野の電停は駅舎は建替えられていますが、雰囲気は昔のままです。1978年当時。
2018年3月17日撮影 伊野


600形603
1958年自社若松工場製。直接制御車で連結器がありません。伊野線の単線区間。伊野線は鏡川橋~伊野が単線になります。
2018年3月17日撮影 咥内


600形604
1958年自社若松工場製。直接制御車で連結器がありません。サイド窓の上段はアルミサッシです。御免線のサイドリザベーション区間です。御免線は西高須~後免西町が一見専用軌道ですが、路面の端で舗装されていない「サイドリザベーション」になります。
2022年10月14日撮影 領石通


600形607
1958年自社若松工場製。直接制御車で連結器がありません。サイド窓の上段はアルミサッシです。2018年は「幕末維新博」のラッピング。丁度、高知城天守をバックに撮影しています。2022年は通常塗装に戻っていました。パンタ側の前面窓はHゴム支持です。1978年にも撮影しています。
2018年3月17日撮影 県庁前


2022年10月14日撮影 田辺島通


600形608
1959年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。「やなせたかし記念館」のラッピング。1978年にも撮影しています。
2022年10月14日撮影 高知城前


600形609
1959年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。「やなせたかし記念館」のラッピング。はりまや橋交差点の御免線電停は「デンテツターミナル前」。
2018年3月17日撮影 デンテツターミナルビル前


600形612
1959年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。1978年にも撮影しています。
2018年3月17日撮影 知寄町二丁目


600形613
1959年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。1974年までここで安芸線と接続しており、直通運転も行われていました。後ろの高架は安芸線の廃止後に建設された土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線。1978年にも撮影しています。
2018年3月17日撮影 御免町


600形614
1959年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。
2024年2月18日撮影 葛島橋東詰~西高須


600形615
1959年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。鏡川を単線の専用橋で渡ります。
2022年10月14日撮影 鏡川橋~鴨部


600形616
1960年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。
2022年10月14日撮影 県庁前


600形617
1960年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。
2018年3月17日撮影 デンテツターミナル前


600形618
1960年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。
2022年10月13日撮影 北浦


600形619
1960年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。
2024年2月18日撮影 西高須


600形620
1960年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。
2018年3月17日撮影 堀詰


600形621
1961年自社若松工場製。間接制御車で連結器があります。サイド窓の上段はアルミサッシです。1978年にも撮影しており、連結運転用のジャンパ線、エアホースが残っていました。1987年までは一部連結運転が残っており、1987年以降に撤去された様です。
2022年10月14日撮影 伊野駅前


600形622
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。1978年にも撮影しており、連結運転用のジャンパ線、エアホースが残っていました。1987年までは一部連結運転が残っており、1987年以降に撤去された様です。
2022年10月13日撮影 北浦~船戸


600形623
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。
2024年2月18日撮影 西高須


600形624
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。
2022年10月14日撮影 梅の辻


600形625
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。葛島橋を渡ります。葛島橋は架け替えられ、昔の面影はありません。
2024年2月18日撮影 知寄町三丁目~葛島橋東詰


600形626
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。
2018年3月17日撮影 文殊通


600形627
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。朝倉電停は高知大学の最寄りです。
2018年3月17日撮影 朝倉


600形628
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。
2022年10月13日撮影 後免中町


600形630
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。
2018年3月17日撮影 知寄町三丁目


600形631
1963年ナニワ工機(現アルナ車両)製。間接制御車で連結器があります。高架はJR土讃線です。1978年と風景はあまり変わっていません。
2018年3月17日撮影 咥内


通票閉塞区間のため、タブレットを携行しています。無線機が付いているのが現代風です。2021年のダイヤ改正でここでの交換は無くなりました。
2018年3月17日撮影 八代(信)


700形
元山陽電気軌道(下関)の700形。1971年の山陽電気軌道の廃止に伴い、3両が譲渡されました。元山陽電気軌道の車両が見られるのはここだけです。
700形701
1958年ナニワ工機(現アルナ車両)製の元山陽電気軌道700形701。
2022年10月14日撮影 鴨部


700形702
1958年ナニワ工機(現アルナ車両)製の元山陽電気軌道700形702。1978年も撮影しています。
2018年3月17日撮影 菜園場町


700形703
1958年ナニワ工機(現アルナ車両)製の元山陽電気軌道700形704。この1両のみ車番が変更されています。
2022年10月13日撮影 御免東町~御免町


800形
700形と同じく、山陽電気軌道の廃止に伴い4両が譲渡されました。700形との違いは製造年度くらいでほとんどありません。
2022年10月14日撮影 県庁前


800形803
1959年ナニワ工機(現アルナ車両)製の元山陽電気軌道800形803。1978年にも撮影しています。桟橋通五丁目電停は以前、何もない吹き曝しでしたが、2009年に整備されました。
2018年3月17日撮影 桟橋通五丁目


800形804
1959年ナニワ工機(現アルナ車両)製の元山陽電気軌道800形804。1978年にも撮影しています。
2022年10月13日撮影 船戸


1000形
1981年に登場した土佐電気鉄道初の冷房車。アルナ工機(現アルナ車両)で2両製造されました。台車、主制御器等の機器は西鉄北方線331形のものを流用しています。
1000形1001
2024年2月18日撮影 桟橋通五丁目


1000形1002
2024年2月18日撮影 西高須


2000形
2000年から200形の置き換え用として導入されました。主要機器類は200形のものを流用しています。
2000形2001
2000年アルナ車両製。200形218の機器を流用。
2018年3月17日撮影 領石通


2000形2002
2004年アルナ車両製。200形217の機器を流用。超低床車100形の導入を挟み、増備されました。
2018年3月17日撮影 葛島橋東詰


2000形2003
2005年アルナ車両製。200形219の機器を流用。
2018年3月17日撮影 領石通


2024年2月18日撮影 知寄町三丁目


3000形3002
2021年アルナ車両製。2編成目の導入です。
2022年10月14日撮影 朝倉


2022年10月14日撮影 はりまや橋


桟橋車庫
1987年に知寄町から移転してきました。そのため、桟橋線で全部の形式を見る事が出来る様になりました。ポルトガル・リスボン市電の910形、オーストリア・グラーツ市電の320形、レプリカ復元の7形が見えます。
2018年3月17日撮影


200形214、211、212、奥に復刻塗装の213が見えます。この4両は1954年日立製作所製でパンタグラフ装備、非冷房です。リスボン市電の910形も見えています。
2022年10月14日撮影 桟橋車庫


2018年10月7日up
2022年10月26日写真追加
2024年2月25日写真追加 レイアウト変更